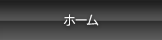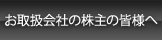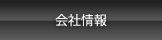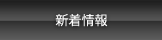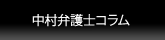中村弁護士コラム 第50回
違法配当事例の増加
弁護士 中村直人
会社法になってから、過失による違法配当の事例がいくつか見られます。これは会社法では、分配可能額の計算がとても分かりにくくなっていることが一因かと思われます。
会社法では、分配可能額の計算は、まず「剰余金」の額を算出し(法446条)、その次にそれを元に「分配可能額」の算出をする(法461条)という2段階の構成になっています。それは何故かと考えるのですが、おそらくそれは「純粋に理論的な帰結だから」というだけのことであって、政策的な意図があるわけではないようです。つまり、分配可能額を算出するにあたっては、いろいろな要素を考えなければいけないのですが、その中には、「剰余金」の額を変動させる要因と「剰余金以外」の勘定科目を変動させる要因の2つがあります。たとえば、自己株式の消却は、その分だけ剰余金の額を減少させます。一方、保有有価証券の評価額は「その他有価証券評価差額金」の勘定科目を変動させますが、剰余金の額を変動させるわけではありません。つまり純粋な会計上の理屈として順番に考えていくと、分配可能額というのは、剰余金の額から、政策的な理由などで減増額すべき勘定科目を増減させて算出することになりますので、まず剰余金の額を変動させる要因によって会計上の剰余金の額が変動し、その後、さらにその他の勘定科目を使用して分配可能額を算出する順序となるわけです。いわば前者は「会社の計算」の問題であり、後者は「分配」の問題であるわけです。だから、剰余金の額の根拠規定である法446条は、「第三節 資本金の額等」の中にあり、分配可能額の根拠規定である法461条は「第六節 剰余金の配当等に関する責任」の中にあるのだと思います(2カ所に分かれているから、また分かりにくいのですね)。
それでは昔の商法はそのようなことはなかったのに、どうして今の会社法はこうなったのかと考えますと、それは今の会社法では配当などの分配が期中いつでもできるようになったからだと思います。昔の商法の時代は、基本的には期末配当だけでしたから、期末の計算書類を基に配当可能利益を計算すれば良かったので「剰余金」の計算と「分配可能額」の計算を二段階に分けてする必要などありませんでした。当時は、総資産から総負債を差し引いて、更に資本金などを差し引けばそれで配当可能利益が算出できるという単純な世界だったわけです。それが期中いつでも配当などができるということになると、期末の計算書類とは別の分配時点で分配可能額を計算しなければなりません。そうすると、期末後分配時点までの様々な会計事項が全部降りかかってきてしまうわけです。それらを全部きちんと整理・計算しようとすると、会計上、剰余金の額を変動させる事項と、それ以外の政策的に分配可能額の額を変動させる事項は当然それぞれ別個に算出されることになってしまうわけです。そこで純粋に会計・計算の世界として剰余金の額がどうなるかという次元の問題と、それらの会計上の各勘定科目の金額を元にどう分配可能額を計算するかという次元の問題に区分されることになりました。
次に、具体的に、分配可能額算出にあたって、分かりにくい規定の趣旨を説明します。まず剰余金の額の計算をしている法446条1号ですが、この規定は、「資産の額」とか、「負債の額」とか、いろいろ足したり引いたりしてとても分かりにくくなっています。しかし、1号がいっていることは、全部差し引きすると、「その他資本剰余金」と「その他利益剰余金」の額の合計額というだけのことです。何故、こんな分かりにくい回り道をするのか到底理解できませんが、要するに、期末の会計上の剰余金の額だというだけの規定なのです。昔、貸借対照表上の総資産の額から総負債の額を引き、更に資本金等を差し引いて配当可能利益を算出していた時代の定め方(控除方式)を踏襲する振りをしながら、実際には控除方式は採らず、必要な勘定科目をピックアップしてその額を足し算引き算する方式(ピックアップ方式)にすり替えたテクニックとでもいうべきでしょうか。
それから実務的に分かりにくいのは、自己株式の取扱い、特に期末後の取得・処分などが絡まった場合ではないでしょうか。その規定の趣旨がよく分からないと、ついつい計算も間違ってしまうものです。順に説明しますと、まず法446条1号の「剰余金」の額の計算にあたっては、自己株式については、この1号では控除されていません。当然ですが、自己株式は会計上剰余金と別立てですから、剰余金の額の計算には入ってきません。法446条2号は、期末後に自己株式を処分した場合の差損益の部分を剰余金の額の増減事由にしています。たとえば、100万円の簿価の自己株式を120万円で処分すると20万円その他資本剰余金が増加します(100万円の簿価の部分は、自己株式がその分なくなるだけです)。つまり「剰余金」の額を変動させる要因としては、自己株式処分の場合は、処分代金額全額ではなく、差損益の部分だけです。そこで446条2号は差損益の部分だけ本条に規定しました(こうやって分けるから分かりにくくなるのですが)。また、法446条5号は、期末後に自己株式を消却した場合にはその簿価を剰余金の額の減額事由にしています。一瞬、「自己株式を消却したのだから、その分分配可能額は増加するはずではないか」と勘違いするかも知れませんが、自己株式を消却すると、その簿価の分だけ、相手勘定として剰余金の額を減少させることになるのです(両落ち)。
一方、分配可能額の計算規定では、法461条2項3号は、自己株式の帳簿価額を減額事由にしています。これは、自己株を保有していれば当然その額の分だけ分配可能額が減額されるべきですが、上記の通り、剰余金の額には自己株の簿価は反映していませんから(まだ控除していない)、ここで控除するわけです。不思議なのは、同項4号は、期末後に自己株式を処分した場合の「当該自己株式の対価の額」を「控除事由」としていることです。何故「控除」事由なのでしょう?自己株式を処分すれば、その代金の分だけ分配可能額は「増加」すべきなのではないでしょうか?
そうなのです。実質的には、自己株式を処分すれば、本来、その分だけ分配可能額は増加すべきなのですが、実は、会社法は、別の要素を考えて、期末後の自己株式処分対価は分配可能額にはしないこととしたのです。どういうことかというと、会社法が心配したのは、期末後に自己株式を処分して対価を受け入れたかも知れないけれども、もしかしたら、その対価は適切な価額ではなく、不当に高い評価額を与えられて処分されたかも知れないということです。そこで自己株式処分対価は、きちんと期末の計算書類や臨時計算書類という形で妥当性が確認されて始めて分配可能額になる、という方針を採ったのです。法461条2項2号ロを見ると、臨時計算書類を作成すれば、自己株処分対価を分配可能額に算入できることとしているのは、その現れです。
さらにその結果、面白い計算をしています。法461条2項3号は、「自己株式の帳簿価額」を減額事由としていますが、この自己株式の帳簿価額は、分配時点のものです。期末時点のものではありません。そのため、期末後に自己株式処分をすると、それは、ここからはずれてしまいます(分配可能額が増加してしまう)。また法446条2号は、前述の通り、自己株式処分差益を剰余金の計算に入れてしまっています。そこで、「期末後の自己株式処分は分配可能額にしない」、という方針を採る以上、期末時点の自己株式の価額を控除事由にしなければならないので、そこで法461条2項4号は、自己株式処分の場合の「対価の額」を控除事由としました。こうすれば、期末時点の自己株式の簿価と、期末後の処分で増加してしまった処分差益の額(剰余金に算入されてしまっている)の両方を消すことができるわけです(簿価+差益=処分対価の額)。要するに、自己株式の取扱いは、処分に関しては、期末時点で固定させる(期末後の処分で分配可能額を増加させない)ということです。
但し、逆に、期末後に自己株式を「取得」した場合は、それはその金額の分だけ分配可能額を使用してしまったわけですから、これは控除しなければなりません。この分は、法461条2項3号が、分配可能額算出時点での「自己株式の帳簿価額」を控除事由としており、もし期末後に自己株式を取得していればそれもここに入ってきますから、ここできちんと除外されることになります。つまり取得に関しては、期末後のものも控除し、処分に関しては、期末ベース、ということです。
利便性向上、利用分析等のためクッキーを使用してアクセスデータを取得しています。
詳しくは「このサイトのご利用について」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。