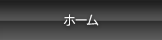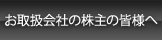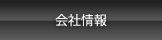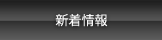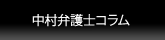中村直人弁護士コラム 第90回
令和元年改正会社法(1)
社外取締役設置義務と社外取締役への業務執行の委任
弁護士 中村直人
今回から、令和元年改正会社法の解説を始めます。最初は、「社外取締役の活用等」とされている項目です。
まず社外取締役の設置義務化があります。改正前は、社外取締役を置いていない会社はその理由の開示を求められていましたが(改正前会社法327条の2)、今回の改正で、有価証券報告書の提出義務のある監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるもの)は、社外取締役を置かなければならないとされました(改正後同条)。すでに多くの上場会社に社外取締役が存在していますから、その点では大きな影響はないところですが、実務で気になるのは、もし社外取締役が欠員となったときはどうなるのだろう、ということです。第一にその補充を考える必要がありますが、①補欠社外取締役の選任をしておく方法、②権利義務取締役(会社法346条1項)となる場合、③一時取締役を選任する方法(同条2項)が考えられます。④として、臨時株主総会を開催して社外取締役を選任する方法も考えられますが、定時総会が近く開催される場合にはそれにより、定時総会まで期間が空いている場合(例えば6か月以上)には臨時株主総会を開催することが考えられると示唆されています(法務省担当官解説・旬刊商事法務2226号8頁)。第2に、社外取締役が欠員の間に取締役会決議ができるのかということも心配になります。この点は、欠員となったとしても、その後なされた取締役会決議が直ちに無効になるわけではなく、合理的な期間内に選任すれば取締役会決議は有効だとされています。ただし、社外取締役の重要性を考えると、裁判所において簡単に決議は有効としてもらえるか、あまり楽観しない方がいいようにも思います。実務的には、複数の社外取締役を選任しておくか、または補欠社外取締役を選任しておくことになると思います。
この改正の面白い点は、改正理由です。本来、社外取締役を法律が強制する以上、それが企業価値の向上やコンプライアンスの向上に有効であるから、などといった実質的な理由が述べられなければならないでしょう。しかし各種調査では社外取締役の存在と企業価値の向上等との間に有意な因果関係は立証されていません。そのため、それを改正理由とすることもできず、結局、社外取締役が一人もいないと経営が独善に走ったり経営者が保身に走るといった危険があるのではないかと株主が心配するからそういう疑念を払拭してわが国資本市場の信頼を向上させる、というのが立法理由になったとされています。
次の改正点は、社外取締役への業務執行の委託の許容です。社外取締役の要件では、業務執行をしないことが必要とされていますので(会社法2条15号イ)、もし社外取締役が業務執行をしたと認定されてしまうと、その人は社外取締役ではなくなってしまいます。しかし実務では、MBOのときの特別委員会や親子会社間取引のときの特別委員会など、類型的に取締役と会社・少数株主の利益が相反する際に、利害関係のない社外取締役にいろいろな職務を果たして頂くことがあります。これが業務の執行に当たるかどうか、学説・判例上、明確ではありませんでした。そこでその疑念を解消しようというのが改正の意図です。改正法348条の2によれば、①会社と取締役の利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、②都度の取締役会の決定により、業務の執行を社外取締役に委託することができる、③ただし、業務執行取締役が社外取締役に指揮命令をしてはいけない、という3つの要件を満たすときには、社外取締役がその業務を執行しても社外取締役としての資格を失わない(会社法2条15号イの「業務を執行した」取締役には当たらないこととする)としました。①は、会社の利益と取締役の利益が相反するのか、少数株主と取締役の利益が相反するのか、いろいろな状況がありますので、言葉遣いを慎重にしています(例えば「株主共同の利益に反する」などという定番文句は使っていません)。
この改正が面白いのは、社外取締役に委託する仕事が「業務の執行」であるかどうかを明確にしたわけではないということです。「○○は業務の執行に当たらない」などという規定を設けたわけではないのです。だから改正後も、ある行為が業務の執行に当たるかどうかは、学説判例によってそれはそれとして形成されていくことになります。最終的に「○○は業務の執行ではない」とされれば、そもそも本条の適用がないことになります。実務的には、まず業務の執行に当たるかどうかを考え、ついで万一当たるとしても上記3要件を満たしていれば、社外取締役の資格は失わないで済む、ということになります。その意味で、セーフ・ハーバー・ルールを定めたのだと解説されています。逆にいえば、①②に定めたような仕事はみな業務執行に当たるのだ、という判断をしたものではないですし、反対解釈をしてそれら以外は業務執行に当たらないのだという解釈もでてこないということです。不思議ですが、「業務の執行を委託した」はずなのに、後日「業務の執行ではなかった」と判断される余地もあるわけです。また最終的に業務の執行に当たると判断され、本条の適用があったときも、社外取締役の資格要件との関係では「業務の執行」に該当しないものとされますが、それ以外の場面では、業務の執行であったことになります。会社法の中には「業務」という用語が多数出てきますが、そちらには影響しないのです。
社外取締役には本条のような規定が設けられましたが、社外監査役については設けられていません。一見、それでは社外監査役はそういう仕事をしてはダメなのか、と反対解釈してしまいそうですが、社外監査役の場合には、そもそも2条15号イのような資格要件の規定がありません。さらに監査役には、業務執行を一律に禁止する規定もなく、それをしていいかどうかは会社法335条2項の兼任禁止の規定に反するかどうかということで議論されています。したがって、社外監査役の資格要件には関係がないので(その行為が監査役の善管注意義務違反や法令違反になるかどうかという問題)、セーフ・ハーバー・ルールを作る必要はなかったのでしょう。
© 2020 Tokyo Securities Transfer Agent Co., Ltd. All rights reserved.
利便性向上、利用分析等のためクッキーを使用してアクセスデータを取得しています。
詳しくは「このサイトのご利用について」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。